皆さん初めまして!次世代ユネスコ国内委員会委員/国際教養大学国際教養学部 学部生の川端優木(かわばたゆうき)です。現在は、フィンランドにあるラップランド大学(University of Lapland)に交換留学生として1年間留学をしています。大学では、教育学と地域開発学を専門に学んでいます。今回のYouthnoteでは、私が韓国で参加したユネスコの国際フォーラムについてご紹介したいと思います。

私は、2024年12月2日~4日の3日間、韓国で開催された「UNESCO International Forum on the Futures of Education 2024」にユース日本代表として出席しました。本フォーラムは、ユネスコ、韓国教育省、韓国ユネスコ国内委員会による主催の下開催され、世界各国から教育関係省庁の官僚、ユネスコ職員、教育開発分野における識者、教職員、そしてユースが集い、「教育の未来」をテーマに議論しました。各国が抱える「現在」の教育問題を議論するだけではなく、「未来」の教育のあり方について様々な見識を共有し合いました。私は次世代ユネスコ国内委員会を代表し、分科会への参加や教育開発分野の第一線で活躍する識者とのネットワーキング活動に力を入れました。

夜の水原華城
本フォーラムの開催地である水原市には、ユネスコ世界遺産に登録されている「水原華城」があります。夜には、水原華城を訪れ、その壮大な城壁と遺跡を散策し、韓国の美しい文化遺産を巡ることができました。

世界各国のユース代表との写真

会場の水原コンベンションセンター
1日目の夜には、韓国政府により戒厳令が発令されるという事態にも見舞われましたが、フォーラムは無事に開催されました。参加者は1,000人を超え、普段の大学の講義では味合えない独特の緊張感を感じました。
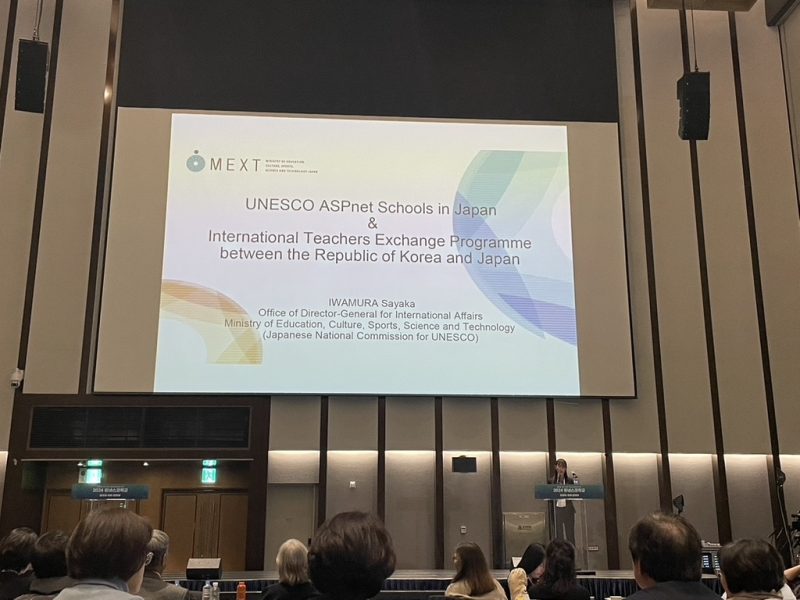
文部科学省による発表
フォーラム中には、「先端科学技術と未来の教育現場」「未来の高等教育のあり方」「ウェルビーイングと教育」といった、様々な視点から「教育の未来」を紐解く分科会やセッションが開催されました。私は参加できる全てのセッションに出席し、全体に共通していた点を発見しました。それが、
①AIをはじめとするデジタル技術を教育に応用する必要性
② 地域コミュニティを活かした教育をデザインする
の2点でした。
AIをはじめとするデジタル技術を教育に応用する必要性

AIと教育に関する分科会の様子
特に「AIと教育」に関する分科会では、AIをどのように教育現場で応用するべきなのか、活発に議論されていました。私も大学で教育学を学ぶなかで、普段の講義で「AIの使用」について議論を行っています。国際フォーラムの場において、現在も議論されているテーマであることに驚いたと同時に、「答えのない問い」であることを肌で感じました。
分科会では、先端科学技術の発展が教育の充実度や教育環境の効率性、教員の業務効率性を大きく向上させる可能性があることが紹介されました。一方で、生成AI等の活用により、子どもたち自身の思考機会を損なう可能性、読み物に触れる機会の減少、そして教師の役割の脆弱化などのリスクに面しているケースが各国から紹介されました。生成AIの活用を、ICT活用やデジタルリテラシー育成の機会と捉え、積極的に推進する研究者もいれば、AI等のテクノロジーが発展する社会の中で、「学校」では生成AIの使用を控え、子どもたちの思考機会を増やすべきと唱える教員もいました。この現場で私は、教育環境が国や地域によって大きく異なることから、「適所適材」の考えでAIを活用していくことが必要なのだと感じました。同時に、教育現場においてAIはあくまでも「手段」であり、人が人を導き、人を育てる教育が今後も必要不可欠だと考えます。AIをどのように「適所適材」として活用し、子どもたちへの学びへ最大限に還元できるのか、AI活用の最適解を世界中の教育現場で研究・実践する必要があることを実感しました。
地域コミュニティを活かした教育をデザインする

化粧水のワークショップ/高校生が開発した化粧水
また、デジタルのみならず「アナログ」の観点も教育の未来にとって必要だと感じました。つまりそれは、地域コミュニティでの「人と人」を通じたコミュニケーションなのではないでしょうか。子どもたちは、学校を通じて地域コミュニティとつながり、学校での学びを実社会で活用する機会を持つことで、学びの意味を見出すことができます。
本フォーラムでは、各国から様々な事例が紹介されていましたが、特に印象に残ったのが、韓国の高校生が開発した化粧品のブースでした。この化粧水は、韓国でよく飲まれる麦ジュースの製造時に発生する残留物を活かして作られます。生徒たちは学校で化学を専門に学んでいることから、「学校での学びを活かし、地域資源を活用して新しいアイデアを創造する」という経験ができていました。「麦ジュースの残留物の有効活用」という、課題解決型の教育デザインがあったからこそ、生徒たちは「地域」という観点を持って、学びを昇華させることができていました。
日本でもESDネットワークを活かし、地域を舞台とした特色ある教育づくりが行われていることから、私は、日本の実践も海外の教育開発に貢献できるのではないかと感じました。各国における「学校の枠」を超えた学びの事例を共有することで、挑戦的で、未来につながるような教育が開発されていくと思いました。そのためにも、予知できない未来の発展に対応できるよう、教育者は「教育のあり方」について常に「発展とローカリティ」の二つの視点から考え、常に変化し続けることが必要だと学びました。
ユースの発信力の重要性

ユースセッションの様子
また、本フォーラムを通じて改めて体感したのが「ユースによる発信」の重要性についてです。フォーラムでは、韓国のユースによる公開討論が行われました。このセッションでは、約半年間にわたるワーキンググループに分かれての議論を経て、ユースによる「教育の未来」に関する発信が行われました。
・デジタル技術と教育のバランスを保つ事の重要性
・公正で平和的かつ持続可能な未来の形成に向け、若者の声を真に反映させること
・ユースがリーダーシップを発揮し、自由に挑戦できる社会環境の整備
以上の3点が特に私の印象に残りました。
日本においても、次世代ユネスコ国内委員会をはじめ、さまざまな機関でユースの声を取り入れた政策策定や活動を行っていますが、今回の国際フォーラムでは、ユースの参画に対する熱量の大きさを体感しました。例えば、エキシビションブースでは、SDGsに関連したオリジナルプリクラ機が設置されていたりするなど、ユースがユネスコ活動について「気軽に」興味を持ち、発信できる工夫がなされていました。また、主催機関である韓国ユネスコ国内委員会ではインスタグラムを運営しており、そのフォロワー数は1.5万人以上と、ユースをターゲットにした情報発信に特に力に入れていることがとても印象的でした。

オリジナルプリクラ機
最後に
フォーラム最終日のクロージングセッションでは、1,000人を超える会場参加者の中から発言できる機会を頂けました。今回、日本代表のユースとして、分科会やセッションに登壇することがなかったため、このようなフォーラムの締め括りの場で発言することができ、非常に嬉しかったです。ここでは、①科学技術の発展に関わらず、教育開発において、「コミュニティ」を意識することの必要性、②各国の教育者の知識を集結し教育を共創することの重要性、の2点について発言しました。このフォーラムの様子は、オンラインでも韓国語とフランス語、そして各言語の手話に翻訳され、私個人の考えが世界中に伝播したことを感じた瞬間でもありました。同時に、もし別の機会があれば、ユースの視点から日本のユースによるユネスコ活動の発信や、今後のユネスコ活動の発展について議論を行いたい、という私自身の目標も持つことができました。
今回の出席をきっかけに、「今」の教育をよりよくするだけではなく、「未来」を意識した教育づくりの重要性について気づくことができました。AIの発展や予測できない環境の変化がある中で、各国の個々の教育者間そして各ネットワークの間で手と手を取り合いながら、共に教育を向上させていく姿勢が未来にとって不可欠であると実感しました。私自身も、フォーラムで得たつながりを大切にしながら、更なる活動に邁進したいと思います。
DATA
| イベント名 | UNESCO International Forum on the Futures of Education 2024 |
|---|---|
| 日時 | 2024年12月2日(月)~4日(水) |
| 場所 | 韓国・水原市 |
| 執筆 | 次世代ユネスコ国内委員会 委員(2024年12月現在)川端優木 |
| 参考URL | https://www.unesco.org/en/renewing-education-transform-future
|

