文部科学省委託「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業(海外展開を行う草の根のユネスコ活動)」の一環として、ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)が2022年度より手掛ける「インクルーシブな地域コミュニティの推進事業」では、神川県愛甲郡愛川町でインクルーシブな学校開発に取り組む「愛川プロジェクト」(日本)、難民を助ける会(AAR Japan)プノンペン事務所によるインクルーシブ教育推進プロジェクト(カンボジア)、PILCD (People’s Initiative for Learning and Community Development) の災害リスク低減と気候変動に対するコミュニティ能力構築プロジェクト(フィリピン)、3ヶ国3団体に参加頂きプロジェクトを進めて参りました。学校、政府、民間企業、市民社会等の多様なステークホルダーと協働しインクルーシブなコミュニティをどのように実現することが出来るか、国内外の事例研究と学び合いを重ねてきました。前回のコラムでは2年目までの活動の紹介を致しました(前回のコラムはこちらから)。今回は、本事業の最終年度、2024年度の活動、特に昨年10月に実施した地域会合について担当者の視点から振り返り、ご紹介させて頂きます。
2024年10月 地域会合 @神奈川県
最終年度である今年度は、本事業の最終成果物である「インクルーシブな地域コミュニティ作り」の理解を体験的にかつ実践的に深める教材「リソースパック」を作成してまいりました(※リソースパックは、次回のコラムにて紹介いたします)。2024年10月には成果物作成の一環として神奈川県教育委員会、愛川町教育委員会に協力頂き、3日間の地域会合を神奈川県で実施しました。
国際シンポジウム「インクルーシブな地域づくりを目指して」
初日は、「インクルーシブな地域づくりを目指して」と題して国際シンポジウムを行いました。2つの基調講演を行い、一人目はインドの元教育行政官であるDr Anupamに、国際的なインクルージョンの潮流について各国の事例も踏まえてお話頂きました。二人目は、神奈川県教育委員会から教育局支援部部長の古島氏をお招きし、神奈川県の取組として「共に学び共に育つ」の表題のもと、県内にて行われてきた「支援教育」について、お話を頂きました。2つの基調講演に共通していたこととして、「子どもの声を聞くことを重視し、それらを踏まえて現場レベルで如何に実行に移すか」という点でした。政策のみが制定されて現場でそれらの真意が行き届かなければ意味をなさないこと、また現場で直接子どもたちに対峙する人たちの声が反映された政策である必要があること、さらに現場で実践する方々をバックアップできる制度や体制を作ること、こうしたことが具体的な事例をもとに共有されました。
基調講演の後に事例報告として、3団体にそれぞれのプロジェクトの報告をして頂きました。愛川プロジェクトについては、愛川町教育委員会が報告されました。外国につながりのある子どもが増えている愛川町の小学校で、全ての子どもが安心・安全に通えるように、学校の支援体制を県・市・地域の団体やコミュニティなど多くの方々を巻き込んで整えていくインクルーシブな学校開発が行われていました。AARのインクルーシブ教育プロジェクトでは、障がいのある子どもが地域の学校に通えるように学校の先生方の理解促進を図っており、一つの学校がインクルーシブな学校に変容していく様子、特に受入れを行う先生方が教師個人、教師間、また行政やコミュニティと対話を重ねインクルーシブな学校へ邁進していく変容のプロセスについて報告されました。PILCDは、フィリピンの小さな島村にあるコミュニティに対して、災害リスクへの強化を通じたコミュニティ全体の能力強化のプロジェクトを行っており、その工程でインクルーシブな視点に基づき脆弱層とされる人々が計画策定から参画し、自分達自身でエンパワーメントを行っていく取組を紹介頂きました。
共通点は、「一人一人の声を聞くこと」からすべてが始まるというところ。子ども一人一人にとって安心できる学校環境とはどいういうものなのか、それぞれに合う支援の形とはどういうものなのか、教員は何を思いインクルーシブ教育に取組んでいてどのような困難に直面しているのか、また脆弱とされるグループの人々はコミュニティに何を望み、コミュニティは何が提供できるのか、まずは対象とされる人々の声を聞き、自分たちにが出来ることは何なのかを問い直すところから始まっていると感じました。個々のニーズを把握し、学校や地域のリソースを再確認し、そのリソースを持ち合い助け合うことで、皆が望む環境を作っていく、それがインクルーシブなコミュニティ作りなのだろうと、シンポジウムを通して感じました。
一方で、個人の声を政策に反映することの難しさ、政策を実現させるための体制構築のあらゆる壁(人的リソースや財源等)も合わせて議論の中では多くあげられ、理想とする姿へ向かうために今後も関係者間で多くの協議を重ねていくことが必要であることも合わせて痛感するシンポジウムとなりました。
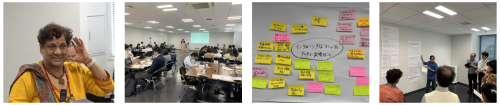
愛川町中津小学校・愛川東中学校の視察
地域会合では、実際のプロジェクトから学ぶべく、愛川町中津小学校・愛川東中学校にも訪問をさせて頂きました。一般的な学校と比べて、圧倒的に外国につながりのある子どもの数が多いと感じたものの、子ども達は国籍など関係なく、皆明るく楽しそうに過ごしている姿が印象的でした。両校は個々のニーズに応じた対応として、日本語の習得度に合わせたカリキュラムの編成や、様々な工夫がなされた日本語教育教材の開発、また地域の方をボランティアとして迎えて行っている日本語のサポート、通常の授業におけるサポート人員の配置や一人一人の先生方の研究、また学校全体として多言語・多文化を歓迎する多文化共生の雰囲気作りなど、あらゆるところ工夫がなされていました。国際教育コーディネーターを配置して、子ども達一人一人と向き合い対話することで、全ての子どもが安心・安全に学校に通えるよう日々尽力されている様子を垣間見ることができました。

3年間のインクルーシブな地域コミュニティの推進事業を通しての学び
教育開発に携わりこれまで「インクルーシブ教育」に国際協力の分野で関わってきた者としては、社会的な弱者とされる子どもたちが学校教育を受容できるようになること、がこれまで多くかかわってきたインクルーシブでした。万人のための教育(EFA: Education for All)、ミレニアム開発目標(MDGs : Millennium Development Goals)、持続可能な開発目標(SDGs : Sustainable Development Goals)、と国際社会における課題が移り行く中で、インクルージョンの捉え方も少しずつ変容してきています。しかし、「インクルーシブ」の根底となるものは「あらゆる人々と共に」という考え方。障がいのある子どもの就学率が着目されたから、障がいのある子どもへの取組としてインクルーシブ教育が語られることが増え、外国につながりのある子どもの数が増えたので、外国につながりのある子どもへの取組が注目されています。女子教育、非識字者への教育、生涯学習や、リスキリング、カテゴリー分けをすると注目される対象となる方が変わってしまいますが、全てにおいて大切なのは、「全ての人がそれぞれの求める教育を受容出来ること」であり、それがインクルーシブな教育であり、様々な形でこれまでもこれからも模索が続くのだろうと感じました。
一方で、留意しなければいけないのは、こうした時代の流れや国際潮流、その国々の課題によって注目される対象が移り行く中で、それ以外の人々は本当にインクルードされているのか、取り残された人はいないのかという視点です。まさにこの事業の発端が、全てのマイノリティとされる方に着目し、インクルージョンの議論に弾かれている人がいないか、対話の場面に参加していたとしても、その人の声をちゃんと聴くことができるのか、という視点でした。手厚く支援をしようとするがゆえに、気づかぬうちに起こりうるエクスクルージョン(排他)を回避するべく、あらゆるステークホルダーと対話し、お互いを深く理解し合うことで、インクルーシブな地域コミュニティを作ろう、というのがこの3年間の事業でした。今回のシンポジウムや視察を通して残された人がいないかと自問をしながら全ての人のニーズを把握しようとする努力の重要性を再認識する機会となりました。
詳細の地域会合報告書はこちらからご覧ください。
次回、本事業の成果品として作成するリソースパックをご紹介します。
DATA
| 執筆 | 福尾(ユネスコ未来共創プラットフォーム事務局) |
|---|

