みなさん、こんにちは。大分県臼杵市(ユネスコ食文化創造都市)出身、次世代ユネスコ国内委員会委員の佐藤世壱です。

GBEF2025絵巻物とのツーショット
石坂産業株式会社でのインターンシップを通じて、Green Blue Education Forum(GBEF)の企画に携わり、当日は次世代ユネスコ国内委員会委員としてパネルディスカッションのモデレーターという貴重な機会をいただきました。あの日、あの場所で生まれた、もっと美しい地球への確かな軌跡をお伝えします。

自己紹介と次世代ユネスコ国内委員会の活動紹介の様子
はじめに:守り残したい環境、創りたい未来のプラットフォーム、GBEF
「未来は、どこか遠くにあるのではない。それは、私たちの足元、それぞれの地域で生まれる小さな「息吹」から始まる。」Green Blue Education Forum(GBEF)は、2019年から始まったGreen Blue Education Forum実行委員会(「体験の機会の場」研究機構内)主催によるフォーラムです。全国のユースが、自身のリアルな「体験」から得た気づきや情熱を社会に発信し、世代や立場を超えた多様な人々との「対話」を通じて、未来を共に創り上げていきます。

「みんなの地球をカラフルに」というテーマには、一人ひとりの個性的な活動や想いが、多彩な絵の具のように混ざり合い、私たちの地球というキャンバスをより豊かで希望に満ちたものにしていく、という願いが込められています。環境省共催のもと、文部科学省、大阪府、日本ユネスコ国内委員会、埼玉県ほかの後援、多くの協賛企業に支えられ、そのコンセプトは2025年8月10日、大阪・関西万博の会場で、約400人の参加者の熱気に包まれ、深い共感が広がる中で体現されました。
第1章:それぞれの地域から始まった、ユースの「My Action」
フォーラムの幕開けは、全国のユースによる具体的なアクションの発表から始まりました。最初のプログラム「My Action! 体験レポート」では、過去の受賞者であるグリーン・スマイル☆キッズの澤崎わかなさん・なのはさん姉妹と、小岩井農牧株式会社の辰巳俊之社長が登壇されました。ここでは、ユースの自発的な地域活動と、企業の専門的な知見が融合することで生まれる、社会課題解決への新たなアプローチが提示されました。澤崎姉妹が盛岡で行うアメリカザリガニの駆除活動が、企業の視点を得て新たな価値を生み出すプロセスとして具体的に報告されました。

澤崎わかなさん・なのはさん姉妹と小岩井農牧株式会社の辰巳俊之社長のコラボレーションによる「My Action! 体験レポート」の様子
続いて「GBEFコンクール」へと移り、全国116団体もの応募の中から最終審査を通過した6チームが、それぞれの想いを込めたプレゼンテーションを繰り広げました。どの活動も、自分たちの足元にある「地域」の課題や魅力に深く根差していました。
環境大臣賞を受賞した富山県の笹島浩聖さん(入善町立入善西中学校)は、「トンボの羽から未来へ」と題し、小学1年生から情熱を注いできたトンボの研究を発表しました。身近な自然を飽くことなく観察し続ける中で、トンボの羽の模様と飛行速度の関係性という神秘を突き止め、その知見を未来の航空技術に応用したいと語る姿は、純粋な探究心がいかに大きな未来を描く力になるかを教えてくれました。笹島さんの原動力は、地域の宝である「杉沢の沢スギ」といった自然環境を守りたいという、地域への深い愛情でした。

入善町立入善西中学校 笹島浩聖さんの発表の様子
公緑クロス機構賞の和歌山県「チームひきよせ」(白浜町立日置中学校)は、「地球を守ろう! 未来を守ろう! 海の森プロジェクト」を発表しました。教室の窓から見える美しい太平洋を守るため、「海のゆりかご」と呼ばれるアマモ場の再生に地域ぐるみで取り組んでいます。そのきっかけが生徒たちの手によるフリーマガジンであったことは、一つの小さな地域活動が多くの人々を「引き寄せ」、大きなうねりを生み出すという、聴衆の心に深く響く物語でした。

白浜町立日置中学校「チームひきよせ」の発表の様子
大和リース賞の愛知県「作庭チームSAKUR☆」(愛知県立猿投農林高等学校)は、「造園の力で持続可能なまちづくり」をテーマに発表しました。地域の地場産業で活用しきれていなかった廃棄石材の可能性に着目し、学んできた造園技術で価値ある資源へと生まれ変わらせ、地域の新たな観光拠点となる公園を創り上げたことを発表。それは、課題を希望へと転換する、未来を創るデザインそのものでした。

愛知県立猿投農林高等学校「作庭チームSAKUR☆」の発表の様子
その他にも、各賞の受賞者から素晴らしい発表が続きました。雲孫賞の京都府立宮津天橋高等学校は、地域の里山(緑)と里川(青)を守り伝える活動を発表。希少植物の保護や、子どもたちを対象とした自然体験「川塾」などを通して、人と自然が豊かに関わり合う未来を目指す姿が印象的でした。石坂産業賞の筑波大学附属坂戸高等学校・中川星空さんは、「生ごみから水素を生み出す」というテーマで、食料廃棄物をクリーンエネルギー源に変えるユニークな研究を発表。加山興業賞の愛知県立安城農林高等学校は、学校で大量に発生するトマトの副産物をブラックソルジャーフライの餌とし、その幼虫を魚の飼料に活用する、革新的な循環システムの構築を報告しました。
全ての発表が、地域のミクロな視点から、地球規模の課題解決というマクロなビジョンへと繋がる、力強い意志と創造性に貫かれていました。
第2章:「壁」を「未来への扉」に変えるトップランナーとの「未来作戦会議」
午後の「未来 Interview & Discussion」では、豪華ゲストを迎え、ユースの情熱を社会実装へと繋げるための、真剣勝負の「作戦会議」が繰り広げられました。昨年度のGBEFで活躍した高校生たちが、活動が直面するリアルな壁について、メディアアーティストの落合陽一氏や一般社団法人公縁クロス機構の森田俊作理事長といった第一人者の方々に、真摯な問いを投げかけました。

未来作戦会議の様子
一つ目の対話は、コーヒーかすを利用したキノコ栽培キットを開発する京都府立桂高等学校から。「どうすればこの商品の需要を作れるか?」という問いに、落合氏が核心を突きました。「コーヒーのカルチャーとキノコの物語は今は遠いかもしれない。ただエコなだけでは人は動かない。例えば、コーヒーミルやタンブラーの形にするなど、コーヒー好きが理屈抜きに『欲しい』と思うデザインモチーフを地域の文化から見つけ出し、物語を接続する必要がある」。その言葉には、思考のOSを書き換えるような、鮮烈な示唆がありました。

落合陽一さんとの対話の様子
二つ目の対話は、農業副産物の循環モデルに取り組む愛知県立安城農林高等学校から。「学校活動をどう社会を動かす力に変えれるか?」という問いに対し、森田理事長は、長年の経験に裏打ちされた実践論で応えられました。「専門的な話も大事だが、社会を動かすのは、もっとシンプルで誰もが価値を理解できるストーリー。『明石の鯛よりうまい鯛ができた』。そういう分かりやすさが、多くの人の『同意』を重ね、『合意』を得る力になる」。

森田理事長との対話の様子
三つ目の対話は、琵琶湖の環境保全のためヘチマたわしなどを広めるLake Biwa protectorsから。「『自分ごと』になっていない人たちをどう巻き込むか?」という切実な問いが投げかけられました。これに対し、森田理事長は企業のロゴマークなどを活用した「自分ごと化」のアイデアを提示。一方、落合氏は「将来、科学的に優れたエコスポンジが登場した時、それでもなおヘチマを選ぶ理由、つまり文化的な価値をどう伝えていくかが重要になるでしょう」と、未来を見据えた本質的な視点を提示されました。

Lake Biwa protectorsの対話の様子
日本のトップランナーの方々がユースの問いに本気で向き合い、未来を創り出すための知が交差する対話は、まさに世代を超えた共創の化学反応であり、GBEFが目指す対話の理想形でした。
第3章:「自分ごと」が繋がり、一枚の絵になる光景
イベントの最終章は、「大好きな地球に私たちができることって何だろう?」をテーマに、会場全体が主役となるディスカッションでした。このセッションで生まれた一体感は、そのプロセスそのものにありました。ユースが自発的に席を立ち、今日初めて出会った会場にいる方々と対話を始めたことをきっかけに、会場の至る所で所属や世代の壁を超えた意見交換の輪が自然発生的に広がっていきました。

会場全体ディスカッションの様子
その光景やGBEFの一連の流れを、一枚の巨大な絵巻物としてリアルタイムで描き出していたのが、グラフィックファシリテーター®のやまざきゆにこさんでした。やまざきさんのペン先から、発表者の情熱的な言葉、会場のざわめき、そして参加者一人ひとりの小さなつぶやきが、次々とカラフルなイラストやキーワードに変換されていきます。その筆先から紡ぎ出される絵と文字は、この日この場所に生まれた無数の想いや対話を、誰もが共有できる一つの物語へと織り上げていました。
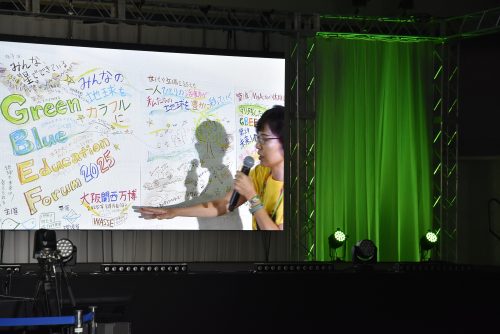
グラフィックファシリテーター®のやまざきゆにこさんの絵巻物の説明の様子
「その大切な地球のために、明日からできるはじめの一歩は?」という最後の問い。その中で、議論の流れを深化させる、本質を突いた意見が会場から表明されました。「色々な活動に取り組む前に、まずは、自然の中に行き、自然に触れることが一番大切なのではないか」。この言葉は、知識や理屈だけでなく、五感で感じる「原体験」こそが全ての原動力になるという、シンプルながらも力強い真実を、会場にいる全ての人に思い出させてくれました。

全体ディスカッションと発表の様子
他にも、「まず『考える』こと自体が、行動の始まりだと思う」「ゴミの分別など、小さなことでも『継続』することが大きな力になる」といった多様な意見が出されました。これらの無数の「自分ごと」が交錯し、共鳴し合い、やまざきさんの絵巻物の上で一つに紡がれていく。それは、まさに「みんなの地球をカラフルに」というテーマが、現実になる瞬間でした。
輝く地球を、次世代への贈り物に
Green Blue Education Forum 2025は、社会変革が遠くにある壮大な目標ではなく、一人ひとりの地域に根差した小さなアクションの連鎖であることを、確かな手応えと共に示してくれました。トンボを愛する心、故郷の海を守りたいという願い、地域の未利用資源の可能性を探究する心。それら地域に根差したミクロな活動が、『対話』という架け橋によって結びつき、磨かれ、やがて世界を変えるマクロな潮流へと成長していく可能性を、私たちは目の当たりにしました。
このフォーラムは、未来へ続くアクションの出発点となるものです。このフォーラムは、私たちがこの星の輝く命を未来へつなぐ責任を再確認し、もっと美しい地球を次世代への贈り物とするための決意を新たにする場となりました。ここで生まれた希望の種が、日本中、そして世界中で芽吹き、私たちの地球をよりカラフルな未来へと導いていくことを、心から期待しています。

GBEF2025年集合写真
DATA
| イベント名 | Green Blue Education Forum 2025~みんなの地球をカラフルに~ |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年8月10日(日) |
| 会場 | 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)EXPOメッセ「WASSE」で開催された「世界遊び・学びサミット」内 |
| 主催 | Green Blue Education Forum実行委員会(「体験の機会の場」研究機構内) |
| 執筆 | 次世代ユネスコ国内委員会(2025年10月現在) 佐藤世壱 |

