みなさん、こんにちは。大分県臼杵市(ユネスコ食文化創造都市)出身、次世代ユネスコ国内委員会委員の佐藤世壱です。
2025年2月上旬、ユネスコ創造都市ネットワークに加盟する大分県臼杵市で、次世代ユネスコ国内委員会委員による「食文化創造都市臼杵ガストロノミーツーリズム」を実施しました。ガストロノミーツーリズムとは、食を通じて地域の文化的背景について学びを深めるツアーのことです。今回は大学生を対象に、特産品や観光資源の視察、地域行政やまちづくり関係者との意見交換に加え、食文化を活用したイベントへの参加や郷土料理の調理体験などを行いました。

臼杵市土づくりセンターにて
慶應義塾大学の学生9名が参加し、臼杵市の協力のもと4泊5日のツアーを実施。視察では、臼杵の食文化の独自性を探り、その社会的価値について議論を深めました。視察の目的は、臼杵市の食文化を基盤とした社会のあり方について学ぶことです。
食文化と地域のつながりを学ぶ―オコメンプロジェクト
参加者は、『慶應義塾大学のオコメンプロジェクト』のメンバーです。このプロジェクトは、湘南藤沢キャンパス(SFC)の学生たちが、キャンパス周辺地域の農家と協力しながら米づくりを行う取組であり、「食は農、農は食〜その土地に根ざした食農文化が暮らしに密接に関わる社会を創る〜」というビジョンを掲げ、日本の農業文化や美しい風景を次世代に継承することを目指しています。
今回のガストロノミーツーリズムは、同プロジェクトの稲作の農閑期を利用し、新たな学びを得るために実施されました。

オコメンプロジェクト 稲作の様子
臼杵の食文化とは?
大分県臼杵市は、「人も環境も健康のもとで食を楽しみ、次世代につなぐまち」という食文化創造都市ビジョンを掲げています。このビジョンには、人と地球の双方が健康になる「プラネタリーヘルス」の考えが息づき、地域循環型の土づくりセンターを運営しながら、今、そして100年後の地域の子どもたちのための農業に取り組んでいます。
臼杵市では、「身土不二(しんどふじ)」の思想を大切にし、その土地でとれる旬の食材を活かした食文化を守り続けています。この考えは学校給食にも取り入れられており、地元の農産物を積極的に活用した献立を通じて、子どもたちに郷土の食の大切さを伝えています。
また、森林涵養に力を入れ、臼杵特有のきめ細やかな水を守りながら、酒・味噌・醤油といった発酵醸造業を発展させてきました。臼杵には神社仏閣を中心とした祈りの文化が根付き、目に見えないものやご縁を大切にする精神が、微生物の発酵を活かした産業とも結びついています。
こうした自然の恵みに加え、江戸時代の臼杵藩による倹約の知恵が今も食文化に息づいています。たとえば、
- お赤飯の代わりにくちなしの実で色付けした「黄飯(おうはん)」
- 魚の中落ちや刺身の切れ端を醤油に漬け、おから(きらす)を「まめし(まぶす)」ことで量を増やした「きらすまめし」
など、限られた食材を無駄なく活用する郷土料理が受け継がれています。
臼杵市は、自然の恵みと発酵文化、そして土地に根ざした知恵を受け継ぐまちです。祈りの文化とともに育まれた食の伝統は、地域の誇りとして、今も息づいています。
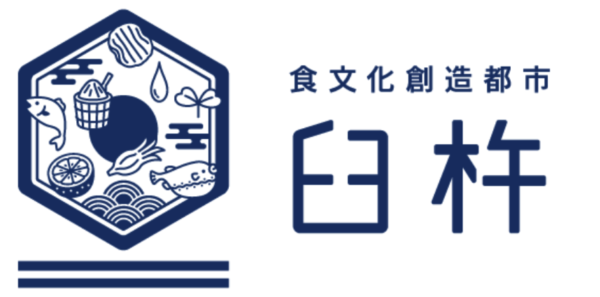
視察の準備—事前学習で理解を深める
臼杵市を訪れる前に、まず臼杵の農と食をめぐる人々の記録映画『100年ごはん』を鑑賞し、さらに臼杵ストーリーブック『掬ぶ』と100年後につなぐ商品として認証される「うすきの地もの」のパンフレットを事前に読み込みました。これにより、地域の歴史や文化について理解を深めた上で、視察に臨みました。

1日目:食文化セッション-臼杵の食文化の価値を学ぶ
初日は「食文化セッション」を実施。臼杵食文化創造都市推進協議会アドバイザーによる講義を通じて、臼杵市がユネスコ創造都市ネットワークに加盟するに至った背景や、その価値について学びました。さらに、臼杵市食文化推進室の方から、加盟の経緯や、市としての取組について詳しくお話を伺いました。
このセッションを通じて、臼杵が「食文化創造都市」として世界に認められるまでの道のりや、その基盤となる価値観について理解を深めることができました。

食文化セッション講義の様子、臼杵市行政職員の方からのお話の様子
2日目:森・土・人をつなぐ学び-土地の恵みと循環を知る
2日目は、地域の中学生の学びの場にもなっている森林の視察からスタート。臼杵市が推進する森林涵養の取り組みについて学び、自然と共生する地域の姿を実感しました。
その後、地域密着型のカフェ「quotidien」を訪れ、地域の方々と意見交換を実施。さらに、土づくりセンターや有機農家を視察し、臼杵市が次世代への投資として赤字覚悟で進める土づくりの取組について担当者の方から話を伺いました。その土を活かし、本物の野菜の美味しさを追求する農業の実践に触れることで、土壌の重要性と農業の本質を学びました。
午後には、伝統工芸・臼杵焼きの工房を見学し、臼杵の歴史とものづくり文化について理解を深めました。

地域の方々と意見交換

臼杵市土づくりセンター
3日目:食文化と映画の出会い—映像を通じて食の本質を考える
3日目は、『100年ごはん』の映画監督・大林千茱萸さんとの対談を行い、映画を通じた臼杵の食文化の魅力や地域づくりについて意見を交わしました。
その後、「うすきの食の映画祭」に参加し、『食べることは生きること』を鑑賞。食と農が命に直結していることや、大地を守る農家の方々の尊さについて改めて考える機会となりました。
午後は、臼杵城下町を散策し、歴史ある町並みや地元の食文化を体験。さらに、酒蔵を訪れ、臼杵の発酵文化がどのように受け継がれてきたのかを学びました。発酵食品が生まれる背景や、微生物の働きを活かした知恵の奥深さに触れることができました。

大林千茱萸さんとの対談

臼杵の城下町
4日目:学びの集大成
最終日は、3日間の視察を通じて得た学びを振り返り、グループごとにKJ法を用いて整理しました。
臼杵市食文化推進室の方々も交えたディスカッションを行い、臼杵の食文化の価値や、それをどのように次世代につなげていくべきかについて意見を交換しました。
また、臼杵の郷土料理である「黄飯」・「かやく」を臼杵の野菜を使って実際に調理し、郷土料理体験を行いました。地域の食を実際に手で作ることで、より深い理解につながりました。

KJ法ワークショップの様子
この4泊5日の視察研修ツアーを通じて、臼杵の食文化が地域の自然や人々の暮らしと深く結びついていることを実感し、その価値をより深く理解する機会となりました。
参加者の振り返り:臼杵の食文化の魅力
参加した学生からは、臼杵の食文化について次のような感想が寄せられました。
「臼杵の食文化をさまざまな角度から考えるきっかけになった。そして、その根底には『美味しいが一番』『健康が一番』という、人間が本来持つべき生き方の本質があることを強く感じた。臼杵の食文化は、大義名分のためにあるのではなく、暮らしに根ざしたものだという点が最も魅力的だと感じる。
また、質素倹約の精神に、その土地らしさを大切にする“身土不二”の考えが融合し、たしかに質素でありながらも、臼杵ならではの華やかさがそこにはある。この点が特に印象に残り、味覚にも、視覚にも、嗅覚にも深く刻まれた。さらに、土地の土・水・空気に合った食材を使い、それを日々口にする人々の暮らしが、長い年月をかけて積み重ねられてきた結果として形成されたのが臼杵の食文化なのだと実感した。」
また、「臼杵の食文化の魅力は、そのストーリー性にあると感じた」という声もありました。伝統と地域の暮らしが織りなす背景が、臼杵の食文化に特別な価値を与えていることが、多くの参加者の印象に残ったようです。

有機農家さんとの交流
視察を通じた意識の変容
今回の視察を通じて、「『食文化』が地域を語る上で大きな力を持つことを改めて実感した」という声もありました。
「これまで、食文化は地域の一要素に過ぎず、それ単独では地域を語ることは難しいと考えていた。しかし、臼杵では、ユネスコ食文化創造都市としての登録にとどまらず、住民の方々の食に対する意識の高さや、長年にわたって受け継がれてきた背景も含めて、『食文化』が地域の個性を強く表現していると感じた。
今回の視察を通じて、食文化を入り口に臼杵の歴史や暮らし、人々の価値観に触れることができたことで、その認識が大きく変わった。食は日々の営みに欠かせないものであり、そこには地域が紡いできた歴史や人々の暮らしが色濃く反映されている。視察を経て、『地域の食文化を知ることは、地域そのものを理解することにつながる』と強く実感するようになった。」
臼杵の食文化が単なる「食」の枠を超え、地域の歴史や価値観、人々の暮らしと密接に結びついていることを深く学ぶ機会となりました。視察を終えた今、参加者は「食文化を知ることは、地域を知ること」と認識を新たにし、それぞれの学びを今後の活動に活かしていくことが期待されます。
視察を終えて—大地を耕し、時を紡ぐ食文化
ガストロノミーツーリズムを通じて、臼杵の食文化が地域の自然や人々の暮らしと深く結びついていることを実感しました。
臼杵の食文化は、単なる食の営みではなく、土地と人が長い年月をかけて築き上げてきた命の循環そのものです。豊かな土壌を育てることは、健やかな作物を生み出すだけでなく、そこに暮らす人々の暮らしを支え、次の世代へと確かな恵みをつなぐことにつながります。
また、発酵の文化は「時間とともに食を育てる」知恵の結晶です。味噌や醤油、酒といった発酵食品は、自然の営みと人の手仕事が響き合い、時をかけて熟成されていく。微生物の目には見えない働きに耳を傾け、最適な環境を整えながら、じっくりと仕上げていく。その繊細な感性と積み重ねられた技術が、臼杵の発酵文化を支えてきました。
今回の視察では、「土を耕し、時間とともに育てる」という臼杵の食文化の真髄に触れました。それは、単なる農業や食品加工の話にとどまらず、「よいものをじっくりと育て、丁寧に受け継ぐこと」の大切さを教えてくれるものでした。
臼杵の食が伝えてくれたのは、目に見えるものだけでなく、見えないものへの敬意、そして「今ここにあるもの」を最大限に生かす質素倹約精神の知恵でした。この学びを胸に、それぞれの場で土を耕し、時間を味方につけながら、自らの文化を築いていくことを心がけていきたいと思います。

有機農家さんの鳥が止まるケール畑
DATA
| 開催日時 | 2025年2月6日(木)~2月10日(月) |
|---|---|
| 執筆 | 次世代ユネスコ国内委員会委員(2025年2月現在)佐藤世壱 |

